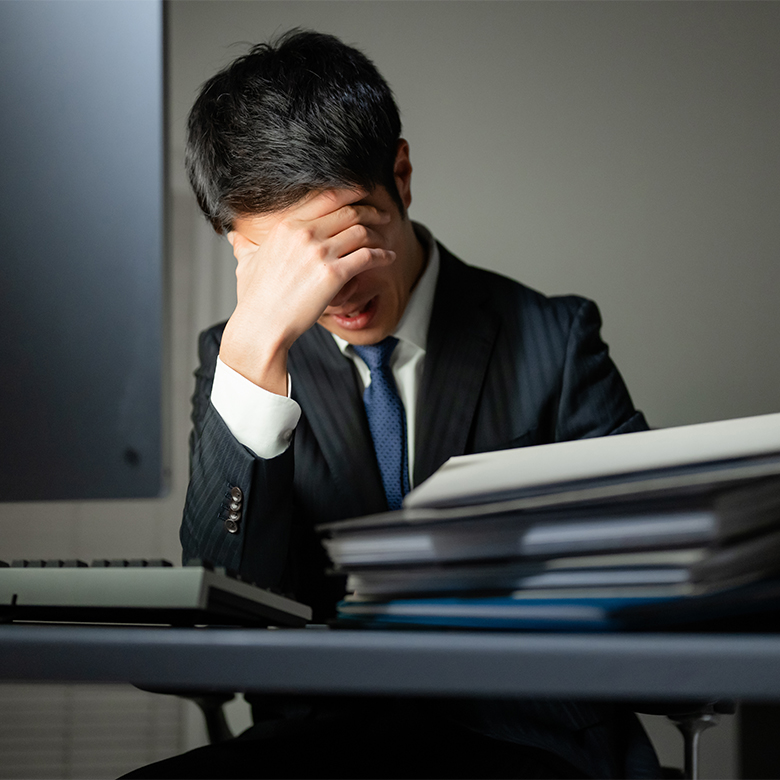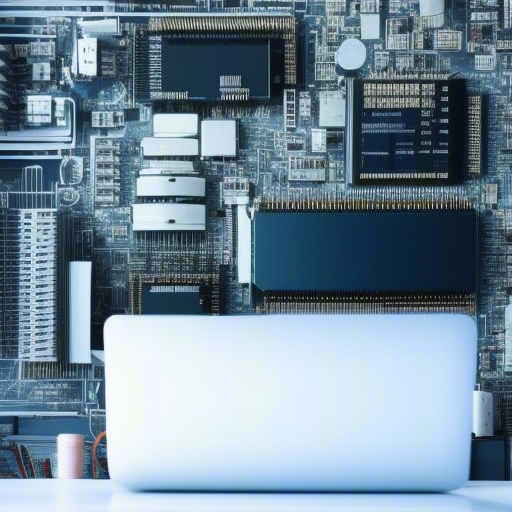マイグレーションとは?【計画から実行、成功のポイントまで徹底解説】

マイグレーションとは
デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の成長に不可欠とされる現代において、「マイグレーション」という言葉を耳にする機会が急激に増えました。しかし、「マイグレーションとは具体的に何を指すのか?」「なぜそれほどまでに重要なのか?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。
マイグレーションは、単なる「お引越し」ではありません。古くなったシステムやインフラを、最新の技術やビジネス環境に適した新しいプラットフォームへと移行させる、戦略的なIT投資です。それは、老朽化し、現代のビジネススピードに対応できなくなった「レガシーシステム」という足枷を外し、企業がデータ活用、迅速なサービス開発、コスト削減、セキュリティ強化といったDX時代の恩恵を最大限に享受するための、未来への架け橋となる重要なプロセスなのです。
経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題、つまり複雑化・ブラックボックス化したレガシーシステムが引き起こす経済的損失のリスクが目前に迫る中、マイグレーションはもはや「いつかやること」ではなく、「今すぐ取り組むべき経営課題」として認識されています。
この記事では、マイグレーションの基本的な概念から、その目的、具体的な種類と手法、そしてプロジェクトを成功に導くための計画立案から実行、運用までの全フェーズを、可能な限り詳細かつ分かりやすく解説します。これからマイグレーションを検討する企業の担当者様はもちろん、DXに関わる全ての方にとって、確かな指針となる情報を提供します
ご質問やサービスに関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
お問い合わせマイグレーションの基礎知識
まず、マイグレーションという言葉の正確な意味と、それがなぜ現代のビジネスにおいて不可欠とされているのか、その背景を深く掘り下げていきましょう。
1-1. マイグレーションの定義と目的
ITにおけるマイグレーション(Migration)とは、直訳すると「移行」「移転」を意味し、既存のシステムやソフトウェア、データを、異なる環境へ移し替える作業全般を指します。この「異なる環境」とは、物理的なサーバーからクラウドへ、古いバージョンのOSから新しいバージョンへ、旧式のデータベースから高性能なデータベースへといった、様々なケースが考えられます。
重要なのは、マイグレーションが単なる「移動」で終わらない点です。その根底には、必ず明確な「目的」が存在します。
-
ビジネス価値の向上: 新しい技術基盤を活用し、データ分析の高度化、新サービスの迅速な市場投入、顧客体験の向上などを実現する。
-
コスト削減: 高額な保守費用がかかる旧式ハードウェアやライセンスから脱却し、運用コストや人件費を最適化する(特にクラウド移行で顕著)。
-
業務効率の改善: 処理速度の向上、手作業の自動化、部門間に散在するデータの統合などを通じて、生産性を向上させる。
-
セキュリティの強化: サポートが終了したOSやミドルウェアが持つ脆弱性リスクを排除し、最新のセキュリティ対策を施した環境へ移行する。
-
事業継続性の確保: 災害やシステム障害に強いクラウド環境への移行や、データバックアップ体制の強化により、ビジネスの継続性を担保する(BCP対策)。
これらの目的を達成するための手段が、マイグレーションなのです。
1-2. マイグレーションと類似用語の違い
マイグレーションを理解する上で、混同されがちな類似用語との違いを明確にしておきましょう。
-
移行: マイグレーションの日本語訳であり、ほぼ同義で使われます。文脈に応じて「システム移行」「データ移行」などと具体的に表現されます。
-
移設: 主に物理的な場所の移動を指します。例えば、自社のデータセンターにあるサーバーラックを、別のデータセンターへ物理的に移動させる場合などが該当します。システムの構成やソフトウェアは変更しない点がマイグレーションとの大きな違いです。
-
移転: 移設とほぼ同義で、物理的な所在地の変更を指すことが多いです。
-
コンバージョン(Conversion): 「変換」を意味し、ある形式のデータやプログラムを、別の形式に変換する作業を指します。例えば、COBOLで書かれたプログラムをJavaに書き換える「言語コンバージョン」や、文字コードの変換などがこれにあたります。マイグレーションプロジェクトの一部としてコンバージョン作業が発生することは頻繁にあります。
-
バージョンアップ/アップデート: 同じ製品やソフトウェアの新しいバージョンに入れ替えることを指します。OSのマイナーアップデートや、アプリケーションの機能追加などが該当します。OSのメジャーバージョンアップ(例:Windows Server 2012から2022へ)など、大規模なものはマイグレーションの一種と捉えられることもあります。
簡単に言えば、マイグレーションは「システムの構成要素や稼働環境に、何らかの質的な変化を伴う移行」と捉えると分かりやすいでしょう。
1-3. マイグレーションが必要となる背景
なぜ今、多くの企業が多大なコストと労力をかけてまでマイグレーションに取り組むのでしょうか。その背景には、避けては通れないいくつかの要因があります。
-
レガシーシステムの限界と「2025年の崖」 長年にわたり企業の基幹業務を支えてきたメインフレームやオフコンなどの古いシステムは「レガシーシステム」と呼ばれます。これらは、度重なる改修によって内部構造が複雑化・ブラックボックス化し、仕様を理解できる技術者も退職。その結果、新しいビジネス要件への対応が困難になったり、維持コストが高騰したり、データが分断されて活用できなかったりといった深刻な問題を引き起こしています。経済産業省は、これらの問題を放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告しており、これが「2025年の崖」問題です。この崖を乗り越えるための最も有効な手段が、レガシーシステムからの脱却、すなわちマイグレーションなのです。
-
DX(デジタルトランスフォーメーション)の本格化 AI、IoT、ビッグデータといったデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革するDXの取り組みにおいて、その土台となるITインフラの柔軟性と拡張性は極めて重要です。しかし、硬直化したレガシーシステムでは、これらの新しい技術を迅速に取り込み、データをリアルタイムに連携・活用することは困難です。DXを本格的に推進するためには、俊敏性の高いクラウド環境などへのマイグレーションが前提条件となります。
-
ハードウェア・ソフトウェアのサポート終了(EOS/EOL) サーバーやOS、データベース、ミドルウェアなど、ITシステムを構成する要素には、メーカーによるサポート期限(End of Service/Life, EOS/EOL)が設けられています。サポートが終了すると、セキュリティパッチの提供が停止し、サイバー攻撃に対する脆弱性が放置されることになります。また、障害発生時にメーカーの支援を受けられなくなるため、事業継続に深刻なリスクをもたらします。このサポート終了のタイミングは、マイグレーションを検討・実施する大きなきっかけとなります。
-
コスト構造の変革と運用効率化 自社で物理サーバーを保有・運用するオンプレミス環境は、資産購入のための初期投資(CAPEX)が大きく、サーバーの維持管理(電気代、設置場所代、保守・運用人件費)に継続的なコストがかかります。一方、クラウドサービスは、利用した分だけ支払う従量課金制(OPEX)が基本であり、インフラの管理をサービス提供事業者に任せられるため、コストの最適化と運用負荷の大幅な軽減が期待できます。このコスト構造の魅力が、クラウドマイグレーションを加速させています。
マイグレーションの種類
マイグレーションは、移行する「対象」と、移行の「手法」によって、様々な種類に分類されます。自社の目的や課題に最適なアプローチを選択するために、これらの種類を理解しておくことが重要です。
【対象による分類】
2-1. データマイグレーション
最も一般的で、多くのマイグレーションプロジェクトに含まれる要素です。古いデータベースやストレージに保存されているデータを、新しいシステムやプラットフォームへ移行します。単にデータをコピーするだけでなく、移行前後のデータ形式の違いを吸収するためのデータクレンジング(不要なデータの削除や重複の整理)、コード変換、フォーマット変換などが必要になる場合が多く、極めて慎重な作業が求められます。データの完全性、一貫性を損なうと、業務に致命的な影響を与えかねません。
2-2. アプリケーションマイグレーション
業務で利用しているアプリケーションソフトウェアを、新しい環境へ移行します。OSやミドルウェアのバージョンアップに伴う移行や、オンプレミス環境で稼働していた業務アプリケーションをクラウド(IaaS/PaaS)へ移行するケースなどが該当します。移行先の環境に合わせてアプリケーションの改修が必要になることもあります。
2-3. OSマイグレーション
サーバーのオペレーティングシステム(OS)を新しいバージョンに入れ替える、または別の種類のOS(例:UNIXからLinuxへ)に変更することを指します。前述の通り、OSのサポート終了(EOS/EOL)が主な動機となります。OSが変更されると、その上で動作するアプリケーションやミドルウェアにも影響が及ぶため、互換性の確認や改修が必要不可欠です。
2-4. データベースマイグレーション
Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQLといったデータベース管理システム(DBMS)を、新しいバージョンや異なる製品、あるいはクラウド上のデータベースサービス(Amazon RDS, Azure SQL Databaseなど)へ移行します。パフォーマンス向上、ライセンスコストの削減、運用負荷の軽減などが主な目的です。データ構造(スキーマ)の変換や、SQLの互換性問題への対応が必要となる場合があります。
2-5. ストレージマイグレーション
ファイルサーバーやSAN(Storage Area Network)ストレージなどに保管されているデータを、新しいストレージ機器やクラウドストレージ(Amazon S3, Azure Blob Storageなど)へ移行します。老朽化した機器のリプレースや、データ容量の増大への対応、災害対策(DR)の強化などが目的です。
2-6. クラウドマイグレーション
近年、最も注目されているマイグレーションです。自社で運用してきたオンプレミス環境のサーバー、ソフトウェア、データなどを、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP) といったパブリッククラウドサービスへ移行することを指します。移行先となるクラウドサービスの形態によって、さらに以下のように分類されます。
-
IaaS(Infrastructure as a Service)への移行: サーバーやストレージ、ネットワークといったインフラ基盤のみをクラウドへ移行する。OS以上のレイヤー(ミドルウェア、アプリケーション)は自社で管理する。
-
PaaS(Platform as a Service)への移行: アプリケーションの実行環境(OS、ミドルウェア、データベースなど)まで含めてクラウドサービスを利用する。開発者はアプリケーションの開発に集中できる。
-
SaaS(Software as a Service)への移行: 既存のパッケージソフトや自社開発システムを廃止し、クラウドで提供されるソフトウェアサービス(例:Salesforce, Microsoft 365)に乗り換える。
【手法による分類:クラウド移行の「6つのR」】
特にクラウドマイグレーションにおいては、米国のIT調査会社ガートナーが提唱した「5つのR」を発展させた「6つのR」と呼ばれる移行戦略がよく知られています。どの手法を選択するかによって、コスト、期間、移行後の効果が大きく変わります。
2-7. リホスト(Rehost)- “Lift & Shift”
最もシンプルで迅速な手法です。既存のサーバー環境を、OSやアプリケーションを含めてほぼそのまま、クラウド上の仮想サーバー(IaaS)へ移行します。アプリケーションのソースコードには手を加えないため、短期間かつ低コストで移行できるメリットがあります。一方で、クラウドの持つスケーラビリティや高機能なサービスといった恩恵を十分に受けられない可能性があります。まずはオンプレミスから脱却したい、という場合に適しています。
2-8. リプラットフォーム(Replatform)- “Lift & Reshape”
リホストに加えて、OSやミドルウェアのバージョンアップ、データベースをクラウドのマネージドサービスに置き換えるなど、クラウド環境に最適化するためのいくつかの改修を行う手法です。アプリケーションのコアなアーキテクチャには手を加えず、クラウドのメリットをある程度享受できるバランスの取れたアプローチです。
2-9. リファクタリング(Refactoring)/ リアーキテクティング(Rearchitecting)
アプリケーションの外部仕様は変えずに、内部構造(アーキテクチャ)を全面的に見直し、クラウドネイティブな設計思想(マイクロサービス化、サーバーレス化など)に基づいて再構築する手法です。開発コストと期間は大きくなりますが、クラウドのメリットを最大限に引き出し、将来のビジネス変化にも柔軟に対応できる俊敏性を獲得できます。DXを本格的に推進したい場合に有効な選択肢です。
2-10. リパーチェス(Repurchase)- “Drop & Shop”
既存の自社開発システムやパッケージソフトウェアを廃棄し、同等の機能を持つSaaS(Software as a Service)製品に乗り換える手法です。例えば、自社で構築した顧客管理システムをSalesforceに切り替える、といったケースが該当します。自社でのシステム開発・運用から解放されるメリットがあります。
2-11. リテイン(Retain)- “Revisit”
現時点ではマイグレーションを行わず、現状のままシステムを維持し続けるという判断です。まだ十分に利用価値がある、あるいは法規制などの理由でオンプレミスに残す必要がある、移行の費用対効果が見合わない、といった場合に選択されます。ただし、将来的に再度移行を検討する必要があるため、定期的な見直しが重要です。
2-12. リタイア(Retire)
現状の分析の結果、そのシステムやアプリケーションがもはや不要であると判断し、完全に停止・廃棄する選択です。機能が重複しているシステムや、利用者がいないアプリケーションなどを整理することで、運用コストを削減できます。
これらの選択肢の中から、アプリケーションの重要度、ビジネス価値、技術的負債の度合いなどを総合的に評価し、最適な移行手法を決定することが成功の鍵となります。
マイグレーションプロジェクトの進め方(計画から実行まで)
マイグレーションは、その規模の大小にかかわらず、一つの大きな「プロジェクト」です。成功のためには、場当たり的な対応ではなく、体系的で緻密なプロジェクトマネジメントが不可欠です。ここでは、一般的なマイグレーションプロジェクトの進め方を4つのフェーズに分けて解説します。
3-1. フェーズ1:企画・計画(アセスメント)
プロジェクト全体の成否を左右する最も重要なフェーズです。ここでの検討が不十分だと、後の工程で手戻りが発生し、予算超過やスケジュール遅延の直接的な原因となります。
-
目的とスコープの明確化: 「何のためにマイグレーションを行うのか?」という目的を、経営層から現場担当者まで、関係者全員で共有します。コスト削減、DX推進、セキュリティ強化など、具体的な目標を数値化できると、後の効果測定も容易になります。「どこからどこまでを移行の対象とするか?」というスコープ(範囲)を定義することも重要です。全てのシステムを一度に移行するのか、特定の部門や業務システムから段階的に進めるのかを決定します。
-
現状分析(As-Is)と課題の洗い出し: 現在のシステム構成を徹底的に調査・可視化します。サーバーのスペック、OSやミドルウェアのバージョン、アプリケーションの構成、データ構造、システム間の連携、ネットワーク構成、現在の運用コスト、業務フローなどを詳細に把握します。このプロセスを通じて、「パフォーマンスが低い」「保守コストが高い」「セキュリティに脆弱性がある」といった現状の課題を具体的に洗い出します。
-
移行先環境(To-Be)の選定・設計: 現状分析と目的を踏まえ、移行後の理想的なシステム環境(To-Beモデル)を設計します。クラウドへ移行するのか、新しいオンプレミス環境を構築するのか。クラウドであれば、どのベンダー(AWS, Azure, GCP)のどのサービスを利用するのか。アプリケーションのアーキテクチャはどうするのか。将来的なビジネスの拡張性も考慮して、最適な移行先を選定・設計します。
-
移行方式の検討: 第2章で解説した「6つのR」などの手法を参考に、対象システムごとに最適な移行方式を決定します。また、システムの切り替え方法も検討します。業務を一度完全に停止して一斉に切り替える「一括移行(ビッグバンアプローチ)」か、新旧システムを並行稼働させながら段階的に移行する「段階移行」か、それぞれのメリット・デメリットを評価して選択します。
-
体制の構築と役割分担: プロジェクトを推進するための体制を構築します。プロジェクトマネージャー、インフラ担当、アプリケーション担当、データベース担当、そしてユーザー部門の代表者など、必要なメンバーをアサインし、それぞれの役割と責任(RACI)を明確にします。専門知識が不足している場合は、外部の専門ベンダーやコンサルタントの協力を得ることも検討します。
-
予算とスケジュールの策定: これまでの検討結果を基に、必要な費用(ハードウェア/ソフトウェア購入費、クラウド利用料、人件費、外部委託費など)を算出し、予算を確保します。また、各工程の作業内容と所要時間を見積もり、マイルストーンを設定した詳細なプロジェクトスケジュールを作成します。
-
リスクの洗い出しと対策: プロジェクトに潜むリスク(技術的な問題、スケジュールの遅延、データの損失、セキュリティインシデント、業務への影響など)を洗い出し、それぞれの発生可能性と影響度を評価します。そして、リスクを回避・低減するための具体的な対策を事前に計画しておきます。
3-2. フェーズ2:設計・開発・テスト
計画フェーズで決定した方針に基づき、具体的な作業を進めていきます。
-
詳細設計: 移行先環境のサーバー構成、ネットワーク設定、セキュリティ設定、監視体制、バックアップ方式、アプリケーションの改修仕様など、具体的なパラメータや手順を詳細に設計し、設計書としてドキュメント化します。
-
移行ツールの選定・開発: データやプログラムの移行を効率的かつ正確に行うためのツールを選定または開発します。クラウドベンダーが提供する移行ツールや、サードパーティ製のツールを活用できる場合も多くあります。
-
移行リハーサルの実施: 本番の移行作業と全く同じ手順で、テスト環境への移行を複数回実施します。リハーサルを通じて、移行手順書の問題点を洗い出して改善したり、作業時間の実測値を取得してスケジュールの精度を高めたり、予期せぬトラブルへの対応策を検討したりします。リハーサルの完成度が、本番移行の成功確率を大きく左右します。
-
テスト計画と実施: 移行後のシステムが要件通りに動作することを確認するため、綿密なテスト計画を立てて実行します。
-
単体テスト: 改修したプログラムなどが個々に正しく動作するかを確認。
-
結合テスト: 複数のシステムやモジュールを連携させた際に、意図通りに動作するかを確認。
-
総合テスト(システムテスト): 本番環境とほぼ同等の環境で、システム全体の性能、信頼性、セキュリティなどを検証。
-
受け入れテスト(UAT): 実際にシステムを利用するユーザー部門が、業務シナリオに沿って操作を行い、問題なく業務を遂行できるか最終確認。
-
3-3. フェーズ3:移行実施(カットオーバー)
入念な準備を経て、いよいよ本番の移行作業を行います。
-
移行スケジュールの最終調整: 業務への影響を最小限に抑えるため、多くの場合は休日や夜間のシステム停止時間を利用して行われます。関係各所への最終的な連絡・調整を行います。
-
データバックアップ: 万が一、移行作業に失敗し、元の環境に戻す(切り戻す)必要が生じた場合に備え、移行直前の完全なバックアップを取得します。これは絶対に省略してはならない重要な工程です。
-
移行作業の実行: 事前に作成・リハーサルした詳細な手順書に基づき、慎重かつ迅速に作業を進めます。プロジェクトメンバー間の連携を密にし、進捗状況と課題をリアルタイムで共有します。
-
切り替え: 移行作業が完了したら、DNSの切り替えなどを行い、ユーザーからのアクセスを新システムに向けます。その後、基本的な動作確認を行い、問題がなければ新システムの稼働を宣言します(カットオーバー)。
3-4. フェーズ4:運用・保守
マイグレーションは、新システムが稼働を開始したら終わりではありません。安定稼働させ、その効果を最大化するための運用フェーズが始まります。
-
移行後の動作確認・安定化: 稼働開始直後は、予期せぬトラブルが発生しやすい期間です。システムの状態を注意深く監視し、問題が発生した際には迅速に対応できる体制を維持します(ハイパーケア)。
-
トラブルシューティング: 発生した問題の原因を特定し、恒久的な対策を講じます。
-
旧システムの停止・廃棄: 新システムが安定稼働したことを確認した後、計画に従って旧システムを停止し、データ消去などを行った上で安全に廃棄します。旧システムを稼働させ続けると、無駄なコストやセキュリティリスクの原因となります。
-
効果測定と評価: 企画・計画フェーズで設定した目標(コスト削減額、パフォーマンス向上率など)が達成できたかを測定・評価します。プロジェクト全体の振り返り(反省会)を行い、得られた知見や教訓をナレッジとして組織に蓄積し、次のプロジェクトに活かします。
マイグレーションを成功させるための重要ポイント
多くの企業がマイグレーションに取り組む一方で、残念ながら計画通りに進まず、失敗に終わるプロジェクトも少なくありません。ここでは、失敗のリスクを最小限に抑え、マイグレーションを成功に導くための特に重要なポイントを8つ挙げます。
4-1. 経営層の理解とコミットメント
マイグレーションは、情報システム部門だけの一存で進められるものではありません。多額の投資が必要であり、全社的な業務改革を伴うことも多いため、経営層がその戦略的重要性を深く理解し、プロジェクトに対して強力なリーダーシップとコミットメントを示すことが不可欠です。予算の確保、部門間の調整、意思決定の迅速化など、経営層の支援がプロジェクト推進の原動力となります。
4-2. 専門知識を持つパートナーの選定
特にクラウドマイグレーションなど、高度な専門知識と経験が求められるプロジェクトでは、自社のリソースだけでは対応が困難な場合があります。実績豊富で信頼できる外部のITベンダーやコンサルティングファームをパートナーとして選定することが、成功への近道です。パートナー選定の際は、単なる技術力だけでなく、自社のビジネスへの理解度や、プロジェクトマネジメント能力、コミュニケーションのスムーズさなども重要な評価基準となります。
4-3. 現状システムの徹底的な可視化
「移行対象のサーバーが何台あるか正確に把握できていない」「誰も仕様書を読んだことがないアプリケーションがある」といった状態では、正確な計画は立てられません。専用のツールなどを活用し、インフラ構成、アプリケーションの依存関係、データ連携のフローなどを徹底的に調査・可視化する「アセスメント」が極めて重要です。この可視化を怠ると、移行計画の見積もりを誤ったり、テスト段階や移行本番で想定外のトラブルに見舞われたりする原因となります。
4-4. 十分なテストとリハーサルの実施
「テストやリハーサルは面倒だから」と省略したり、不十分なまま本番を迎えることは、失敗プロジェクトの典型的なパターンです。特に、性能要件が厳しい基幹システムや、大量のデータを扱うシステムの移行では、本番同等の負荷をかけたパフォーマンステストや、何度も繰り返す移行リハーサルが不可欠です。ここで発見された問題は、本番前に解決できる「宝」だと捉えるべきです。
4-5. ユーザー部門との密な連携
システムは、それを利用する「人」がいて初めて価値を生みます。マイグレーションは、ユーザーの業務プロセスや操作性に影響を与えることが多いため、プロジェクトの初期段階からユーザー部門を巻き込み、意見をヒアリングし、密に連携を取りながら進めることが重要です。特に、受け入れテスト(UAT)では、ユーザー部門に主体的に参加してもらい、実際の業務に支障がないかを確認してもらう必要があります。情報システム部門の独りよがりなプロジェクトは、まず成功しません。
4-6. データ移行の品質確保
システムの入れ物は新しくなっても、中身であるデータが不正確であったり、欠損していたりしては意味がありません。データマイグレーションは、プロジェクトの中でも特に繊細でリスクの高い作業です。移行元と移行先でのデータ件数や内容の整合性を担保するための検証(データバリデーション)の仕組みを確立し、品質を確保することが絶対条件です。
4-7. セキュリティ対策の徹底
新しい環境へ移行する際は、セキュリティ要件も最新の脅威に合わせて見直す絶好の機会です。特にクラウド環境では、オンプレミスとは異なるセキュリティの考え方(責任共有モデルなど)を理解し、適切なアクセス制御、データの暗号化、脆弱性管理、監視体制などを設計・実装する必要があります。移行作業中のデータ漏洩などにも細心の注意を払わなければなりません。
4-8. 移行後の運用を見据えた計画
システムを移行して終わり、ではありません。移行後の新しい環境での運用・保守体制やプロセスを、事前に設計しておくことが重要です。誰が、どのようにシステムを監視し、障害発生時にどう対応するのか。バックアップやリストアの手順はどうなるのか。クラウドサービスを利用する場合は、コストを最適化するための管理手法も必要になります。運用設計が不十分だと、せっかく移行しても、かえって運用負荷が増大してしまうという事態に陥りかねません。
【事例紹介】マイグレーションの成功例と失敗例から学ぶ
理論だけでなく、実際の事例から学ぶことで、マイグレーションへの理解はさらに深まります。ここでは、典型的な成功例と失敗例をいくつか紹介します。
5-1. 成功事例:老朽化した基幹システムをクラウドへリフト&シフトし、段階的に刷新
-
課題: ある製造業では、20年以上前に構築したオンプレミスの基幹システム(販売管理、生産管理)が老朽化。ハードウェアの保守期限切れが迫り、度重なる改修でシステムが複雑化。データが分散し、全社的な経営状況の把握に時間がかかっていた。
-
アプローチ: まずは、ハードウェアの保守切れ問題を解決するため、アプリケーションには手を加えず、クラウド(IaaS)へリホスト(Lift & Shift)することを決定。これにより、インフラの運用負荷とコストを削減。その後、クラウド上で安定稼働させながら、次のステップとして、機能ごとにマイクロサービス化を進めるリファクタリング(段階的な刷新)計画を立てた。
-
成果: ハードウェア保守切れのリスクを回避し、インフラコストを30%削減。段階的なアプローチを取ることで、大規模な一括開発のリスクを抑えつつ、ビジネスニーズに合わせて俊敏に新機能を追加できる基盤を構築。全社データ連携も容易になり、経営判断の迅速化に繋がった。
5-2. 成功事例:オンプレミスのデータウェアハウスをクラウドのマネージドサービスへ移行
-
課題: ある小売業では、オンプレミスでデータウェアハウス(DWH)を運用していたが、データ量の急増により、夜間バッチ処理が翌日の始業時間までに終わらないという問題が発生。また、高価なDWH専用アプライアンスのライセンス費用や運用負荷も大きな負担となっていた。
-
アプローチ: 性能と拡張性に優れたクラウドのDWHサービス(Amazon Redshift, Google BigQueryなど)へのマイグレーションを決断。リプラットフォームの手法を用い、データ連携の仕組み(ETL)もクラウドネイティブなツールに見直した。
-
成果: データ処理性能が劇的に向上し、夜間バッチ処理が数時間で完了。必要な時に必要なだけ計算リソースを拡張できるため、突発的な分析ニーズにも柔軟に対応可能になった。ライセンス費用と運用人件費を合わせて、TCO(総所有コスト)を大幅に削減できた。
5-3. 失敗事例:不十分なアセスメントによる計画の見誤り
-
課題: ある金融機関が、サポート終了を機にレガシーシステムをオープン系システムへマイグレーションするプロジェクトを開始。
-
経緯: しかし、プロジェクト開始前の現状分析(アセスメント)が不十分で、既存システムの複雑な業務ロジックや、他システムとの密な連携関係を完全には把握できていなかった。開発を進める中で、想定外の要件や改修箇所が次々と発覚。その結果、手戻りが頻発し、スケジュールは大幅に遅延。最終的には当初予算の2倍以上のコストがかかってしまった。
-
教訓: プロジェクト初期段階での徹底した現状分析の重要性。見えない部分を安易に「大丈夫だろう」と楽観視することの危険性を示している。
5-4. 失敗事例:ユーザー部門との連携不足による手戻りと混乱
-
課題: あるサービス業が、業務効率化を目的に、自社開発の顧客管理システムをSaaS製品へリパーチェス(乗り換え)することを決定。
-
経緯: 情報システム部門主導でプロジェクトを進め、機能要件の比較だけでSaaS製品を選定。しかし、実際の業務を行っているユーザー部門へのヒアリングや、プロトタイプを使った操作性の確認を怠った。移行後、ユーザーから「以前のシステムにあった機能がない」「操作が複雑で使いにくい」といった不満が噴出。結局、業務が回らなくなり、追加でカスタマイズ開発を行う羽目になったり、一部業務で旧システムを使い続けざるを得ない状況に陥った。
-
教訓: システムはあくまで業務のためのツールであり、その主役はユーザーであるという視点の欠如。プロジェクト初期からユーザー部門を巻き込み、協働で進めるプロセスの重要性を示している。
マイグレーションのトレンドと今後の展望
マイグレーションを取り巻く技術や考え方も、日々進化しています。最後に、今後のマイグレーションの方向性を決定づける重要なトレンドを紹介します。
6-1. クラウドネイティブ化への流れ
単にシステムをクラウドへ「移す」だけでなく、クラウドの能力を最大限に活用できるような設計思想、すなわち「クラウドネイティブ」なアプリケーションへと変革していく流れが加速しています。これは、コンテナ化やマイクロサービス、サーバーレスといった技術を前提とし、変化に強く、復元力の高いシステムを構築することを目指すものです。今後のマイグレーションは、リファクタリングやリアーキテクティングの重要性がますます高まっていくでしょう。
6-2. 自動化ツール・サービスの活用
かつては手作業が多くを占めていたマイグレーションですが、近年はプロセスを自動化するツールやサービスが充実してきています。現状システムの構成を自動で可視化するアセスメントツール、ソースコードを他言語へ自動変換するコンバージョンツール、クラウドへの移行作業を支援する各クラウドベンダー提供のサービスなどです。これらのツールを賢く活用することで、マイグレーションの期間短縮、コスト削減、ヒューマンエラーの削減が期待できます。
6-3. コンテナ技術(Docker, Kubernetes)の利用
アプリケーションをOSやインフラから分離してパッケージ化する「コンテナ」技術(Dockerが代表的)と、そのコンテナを大規模環境で効率的に管理・運用するための「コンテナオーケストレーション」ツール(Kubernetesが事実上の標準)の活用が急速に広がっています。コンテナ化されたアプリケーションは、オンプレミスや特定のクラウドベンダーに縛られることなく、様々な環境への可搬性(ポータビリティ)が高まります。レガシーアプリケーションをコンテナ化してクラウドへ移行する、といったアプローチも増えています。
6-4. マイクロサービスアーキテクチャへの移行
一枚岩で巨大なアプリケーション(モノリシックアーキテクチャ)を、小さなサービスの集合体として分割・再構築する「マイクロサービスアーキテクチャ」への移行も大きなトレンドです。サービスごとに独立して開発・デプロイ・スケールできるため、ビジネスの変化に迅速に対応できる俊敏性が得られます。レガシーシステムのマイグレーションにおいて、リファクタリングを行う際の有力な設計パターンとなっています。
まとめ
本記事では、「マイグレーションとは何か」という根源的な問いから始め、その種類、手法、具体的なプロジェクトの進め方、成功のポイント、そして未来のトレンドに至るまで、包括的に解説してきました。
改めて強調したいのは、マイグレーションが単なるITインフラの入れ替え作業ではなく、企業の競争力を左右する極めて戦略的な経営判断であるということです。それは、過去から受け継いできた技術的負債を解消し、DXという新たな成長軌道に乗るための、未来への投資に他なりません。
マイグレーションの道のりは、決して平坦ではありません。緻密な計画、高度な技術、そして何よりも関係者全員の強い意志と協調が求められます。しかし、その先に待っているのは、変化に強く、俊敏で、コスト効率に優れた、新しいビジネス価値を創造し続けるための強力なIT基盤です。
「2025年の崖」が目前に迫る今こそ、自社のシステムを改めて見つめ直し、未来に向けたマイグレーションへの第一歩を踏み出すべき時ではないでしょうか。この記事が、その挑戦の一助となれば幸いです。