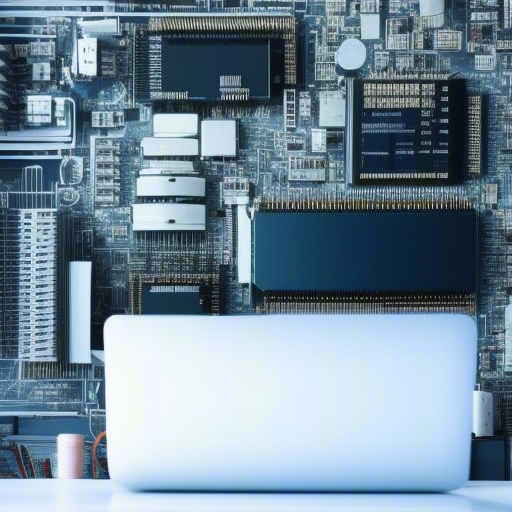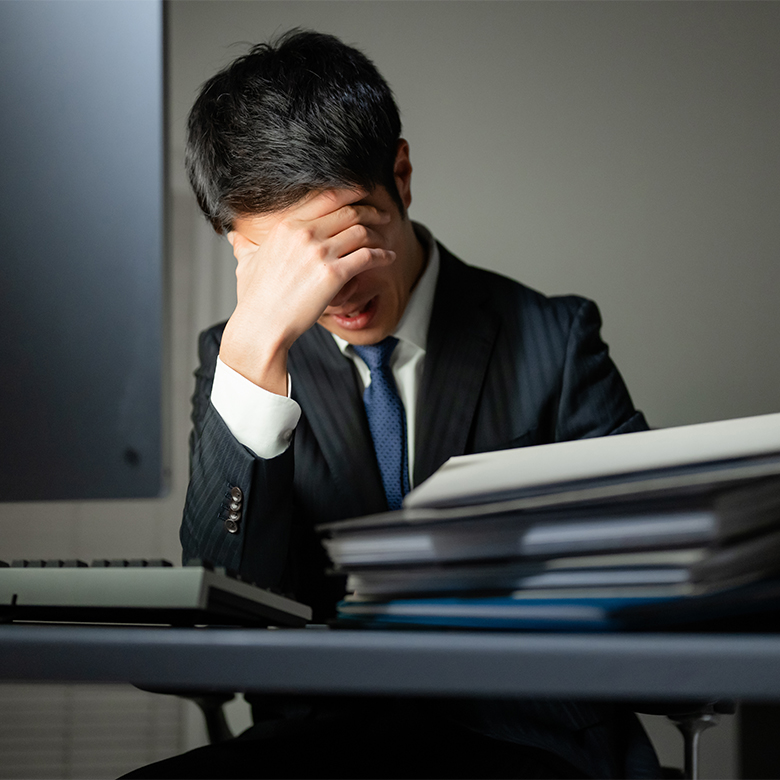システム開発の種類を解説!最適な手法・契約・アプローチの選び方を徹底解説

システム開発とは
現代のビジネスにおいて、システム開発はもはや単なる業務効率化のツールではありません。企業の競争力を左右し、新たなビジネスモデルを創出するための根幹をなす、極めて重要な経営戦略です。しかし、その一方で「多額の費用を投じたのに、完成したシステムが全く使えない」「開発が計画通りに進まず、予算も納期も大幅に超過してしまった」といった失敗談が後を絶たないのも事実です。
なぜ、このような失敗が起こるのでしょうか。その最大の原因の一つが、プロジェクトの目的や特性に合わない「システム開発の種類」を選択してしまうことにあります。
一口に「システム開発」と言っても、その進め方である「開発手法」、外部パートナーとの関わり方を決める「契約形態」、そしてシステムを実現する「開発アプローチ」など、様々な「種類」が存在します。これらはそれぞれに一長一短があり、「絶対にこれが正しい」という万能薬(銀の弾丸)は存在しません。
例えば、絶対に仕様変更が発生しない大規模な基幹システムの開発と、ユーザーの反応を見ながら改善を繰り返していく新規Webサービスの開発では、最適な進め方は全く異なります。前者で後者の手法を、あるいは後者で前者の手法を取れば、プロジェクトは高い確率で混乱し、失敗へと向かうでしょう。
この記事では、システム開発を検討している企業の担当者様や、IT業界に足を踏み入れたばかりの方々が、システム開発の全体像を体系的に理解できるよう、あらゆる「種類」を網羅的に、そして深く掘り下げて解説します。それぞれの特徴を正しく理解し、自社のプロジェクトに最適な選択をするための一助となれば幸いです。
ご質問やサービスに関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
お問い合わせ【開発手法】システム開発の進め方とモデルの種類
システム開発プロジェクトをどのように進めていくか、その設計図となるのが「開発手法(開発モデル)」です。ここでは、代表的な開発手法の特徴と、それぞれがどのようなプロジェクトに適しているのかを詳しく見ていきましょう。
1-1. ウォーターフォール開発モデル
ウォーターフォール開発は、古くから多くのシステム開発で採用されてきた、最も伝統的で基本的な手法です。その名の通り、水が滝(ウォーターフォール)のように上から下へ流れるごとく、工程を一つずつ順番に進めていく点に特徴があります。
工程の流れ:
-
要件定義: システムに何が必要か、どんな機能を持たせるかを決定する。
-
外部設計(基本設計): ユーザーから見える部分(画面、帳票など)の仕様を設計する。
-
内部設計(詳細設計): システム内部の動作や機能の実現方法など、開発者向けの仕様を設計する。
-
実装(プログラミング): 設計書に基づき、プログラミングを行う。
-
テスト: 完成したシステムが設計通りに動作するかを検証する。
-
リリース(導入): 完成したシステムを本番環境へ導入し、運用を開始する。
原則として、前の工程が完全に完了しないと次の工程には進めません。 そして、後の工程で前の工程の不備が見つかった場合、滝を逆流するかのような大きな手戻りコストが発生します。
-
メリット:
-
計画性に優れる: 各工程でやるべきことが明確なため、スケジュールや進捗の管理がしやすい。
-
品質を確保しやすい: 各工程で成果物(ドキュメント)が作成されるため、品質の検証やレビューが行いやすい。
-
大規模開発に対応可能: 全体の見通しが立てやすいため、大人数が関わる大規模なプロジェクトに向いている。
-
-
デメリット:
-
仕様変更に極めて弱い: 開発途中で仕様変更が発生すると、前工程に戻って設計からやり直す必要があり、大幅な手戻り(コスト増・納期遅延)が発生する。
-
開発期間が長期化する: 全ての工程を順番に進めるため、ユーザーが実際に動くシステムを目にするのは最終段階になる。
-
要求のズレが最後に発覚するリスク: 最終段階で「思っていたものと違う」となっても、修正は非常に困難。
-
-
向いているプロジェクト:
-
開発前に仕様や要件を完全に確定できるプロジェクト(例:法律や制度に基づくシステム、業務内容が固定的な基幹システムのリプレイス)
-
人命に関わるなど、極めて高い品質と信頼性が求められるプロジェクト(例:医療機器や金融機関の勘定系システム)
-
大規模で参加メンバーが多いプロジェクト
-
1-2. アジャイル開発モデル
ウォーターフォール開発の課題、特に「仕様変更への弱さ」を克服するために生まれたのがアジャイル開発です。アジャイル(Agile)とは「素早い」「俊敏な」という意味で、その名の通り、変化に迅速に対応しながら開発を進めることを重視します。
アジャイル開発では、システム全体を一度に完成させるのではなく、「イテレーション」または「スプリント」と呼ばれる1〜4週間程度の短い開発期間を何度も繰り返します。この短いサイクルの中で「計画→設計→実装→テスト」の全工程を回し、動作するソフトウェアを少しずつ、反復的に開発・リリースしていくのが最大の特徴です。
このアプローチの根底には、2001年に提唱された**「アジャイルソフトウェア開発宣言」**があります。
プロセスやツールよりも個人と対話を、 包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを、 契約交渉よりも顧客との協調を、 計画に従うことよりも変化への対応を、 価値とする。
-
メリット:
-
仕様変更に強い: 短いサイクルで開発とレビューを繰り返すため、途中で発生した仕様変更や新たな要求に柔軟に対応できる。
-
早期リリースが可能: 優先度の高い重要な機能から開発し、早い段階でユーザーに価値を提供できる。
-
顧客満足度の向上: 開発プロセスに顧客(ユーザー)が深く関与し、フィードバックを反映しながら開発を進めるため、「作ってみたら違った」というリスクを最小化できる。
-
リスクの低減: 問題を早期に発見・修正できるため、プロジェクトが破綻するリスクを抑えられる。
-
-
デメリット:
-
全体の進捗やスケジュールが見えにくい: 開発の方向性が途中で変わる可能性があるため、厳密な納期や全体のスケジュール管理は難しくなる。
-
ドキュメントが少なくなりがち: 「動くソフトウェア」を重視するため、仕様書などのドキュメント作成が後回しにされ、システムの全体像が分かりにくくなることがある。
-
顧客の積極的な協力が不可欠: 頻繁なレビューやフィードバックなど、顧客側のコミットメントがプロジェクトの成否を大きく左右する。
-
-
向いているプロジェクト:
-
開発前に仕様や要件が固まっていない、あるいは変化する可能性が高いプロジェクト(例:新規事業のWebサービス、市場の反応を見ながら改善するスマホアプリ)
-
ユーザー体験(UI/UX)が重要なプロジェクト
-
技術的な不確実性が高いプロジェクト
-
アジャイル開発の代表的な手法
アジャイル開発はあくまで考え方や原則であり、その具体的な実践方法として、いくつかの「手法(フレームワーク)」が存在します。
(1) スクラム(Scrum) ラグビーの「スクラム」のように、チームが一体となってゴールを目指すことから名付けられた、最も普及しているアジャイル開発手法です。スクラムでは、以下の3つの役割、5つのイベント、3つの作成物を定義してプロジェクトを推進します。
-
3つの役割:
-
プロダクトオーナー: 開発する製品の価値を最大化することに責任を持つ。開発する機能の優先順位リスト(プロダクトバックログ)を管理する。
-
開発チーム: プロダクトを実際に開発する専門家集団(3〜9人程度)。自己組織化されており、自分たちで仕事の進め方を決定する。
-
スクラムマスター: スクラムのプロセスが正しく実践されるよう支援する。チームが直面する障害を取り除く「サーバント・リーダー(奉仕型リーダー)」。
-
-
5つのイベント:
-
スプリント: 1ヶ月以下の決められた期間。この期間内に価値のある「インクリメント(完成品の一部)」を作成する。
-
スプリントプランニング: スプリントの開始時に、そのスプリントで何を作るかを計画する。
-
デイリースクラム: 毎日15分の短いミーティング。進捗の確認と、課題の共有を行う。
-
スプリントレビュー: スプリントの終了時に、完成したインクリメントをステークホルダー(利害関係者)にデモし、フィードバックを得る。
-
スプリントレトロスペクティブ(振り返り): スプリントレビューの後、チームでスプリントの進め方を振り返り、次のスプリントに向けて改善点を見つける。
-
-
3つの作成物:
-
プロダクトバックログ: 製品に必要な機能や要件を優先順位順に並べたリスト。プロダクトオーナーが管理する。
-
スプリントバックログ: 1つのスプリントで開発チームが完成させると決めたタスクのリスト。
-
インクリメント: スプリントで完成した「動くソフトウェア」の断片。
-
(2) カンバン(Kanban) トヨタ自動車の生産方式を起源とする手法で、「見える化」を最大の特徴とします。 タスクを付箋(カード)に書き出し、「ToDo(未着手)」「Doing(作業中)」「Done(完了)」といったステータスが書かれたボード(カンバン)上で移動させることで、チーム全体の作業状況を可視化します。 また、「WIP(Work In Progress)制限」というルールを設け、「Doing(作業中)」のタスク数を制限することで、一つのタスクに集中し、作業の滞留(ボトルネック)を防ぎます。
(3) XP(エクストリーム・プログラミング) アジャイル開発の中でも、特に技術的なプラクティス(実践)を重視する手法です。代表的なプラクティスには以下のようなものがあります。
-
ペアプログラミング: 2人のプログラマーが1台のコンピューターで共同作業する。品質向上と知識共有に繋がる。
-
テスト駆動開発(TDD): プログラムのコードを書く前に、そのコードが満たすべきテストコードを先に書く。
-
リファクタリング: 外部からの見た目を変えずに、内部のコードを継続的に改善し、綺麗に保つ。
1-3. プロトタイプ開発モデル
プロトタイプ(試作品)を早期に作成し、ユーザーに実際に触ってもらうことで、完成イメージの共有や要求の確認を行う手法です。ウォーターフォール開発の「要件定義」フェーズを補強する目的で使われることが多いです。
-
メリット:
-
認識のズレを防げる: ドキュメントだけでは伝わりにくい画面デザインや操作感を、早い段階でユーザーと共有できるため、「思っていたものと違う」という手戻りリスクを大幅に低減できる。
-
ユーザーの潜在的な要求を引き出せる: 実際に動くものを見ることで、ユーザー自身も気づいていなかった新たな要望や改善点が見つかりやすくなる。
-
-
デメリット:
-
プロトタイプの扱いに注意が必要: あくまで試作品であるプロトタイプを、そのまま製品として開発してしまうと、後々の拡張性や保守性に問題が生じることがある。
-
開発コストが増加する可能性がある: プロトタイプの作成に時間がかかりすぎると、全体のコストが増加する。
-
-
向いているプロジェクト:
-
画面のUI/UX(使いやすさ、見た目)が非常に重要なシステム
-
これまで世の中になかった、全く新しい概念のシステム
-
発注者側がシステム要件を明確に定義できない場合
-
1-4. スパイラル開発モデル
システムの開発を機能単位に分割し、分割した機能ごとに「設計→プログラミング→テスト」というサイクルを何度も繰り返しながら、徐々にシステム全体を完成させていく手法です。らせん(スパイラル)を描くように開発が進むことから、この名が付きました。 アジャイル開発と考え方は似ていますが、より大規模な開発を想定し、各サイクルの終了時に厳密な評価とリスク分析を行う点が特徴です。
-
メリット:
-
リスクの早期発見と対応が可能: 重要な機能やリスクの高い機能から開発を進めることで、プロジェクトの致命的な問題を早期に発見できる。
-
仕様変更に比較的柔軟: サイクルを繰り返す中で、顧客からのフィードバックを反映しやすい。
-
-
デメリット:
-
プロジェクト管理が複雑になる: 複数のサイクルを管理する必要があるため、高度なプロジェクトマネジメント能力が求められる。
-
小規模な開発には不向き: 管理コストが大きくなるため、小規模なプロジェクトではかえって非効率になる。
-
-
向いているプロジェクト:
-
仕様が不明確で、技術的なリスクも高い大規模プロジェクト
-
官公庁や研究機関などの先進的なシステム開発
-
1-5. V字開発モデル
ウォーターフォール開発の派生形で、特にテスト工程を重視するモデルです。開発工程(要件定義、設計など)とテスト工程(受け入れテスト、結合テストなど)をV字に対応させて考える点に特徴があります。 例えば、「外部設計」の段階で、それに対応する「結合テスト」の計画や設計を並行して行います。これにより、各開発工程で何を確認すべきかが明確になり、テストの品質と精度を高めることができます。
-
向いているプロジェクト:
-
絶対にバグが許されない、品質が最重要視されるシステム(例:自動車のエンジン制御、工場の生産ライン制御などの組み込みシステム)
-
外部に開発を依頼する際の種類
システム開発を自社内だけで完結させる企業は少なく、多くの場合、外部の開発会社(ITベンダー、Sler)に依頼することになります。その際に結ぶ契約の「種類」は、プロジェクトの進め方や責任の所在を大きく左右する重要な要素です。
2-1. 請負契約
**「成果物の完成」**を目的とする契約です。開発会社は、契約時に定めた仕様、金額、納期に基づき、システムを完成させる義務を負います。もし期間内にシステムが完成しなかったり、完成品に欠陥(バグなど)があったりした場合は、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を負い、無償での修正や損害賠償に応じる必要があります。
-
メリット(発注者側):
-
成果物が保証される: 契約通りにシステムが納品されることが保証されている。
-
予算が確定しやすい: 事前に見積もりを取るため、開発にかかる総額を把握しやすい。
-
管理工数が少ない: 開発の進捗管理やメンバーの管理は、基本的に受注者側(開発会社)の責任で行われる。
-
-
デメリット(発注者側):
-
仕様変更に弱い: 契約後に仕様を変更する場合、追加費用や納期の見直しが必要となり、柔軟な対応が難しい。
-
ベンダーに丸投げになりがち: 開発プロセスが見えにくく、ベンダー任せになってしまうリスクがある。
-
見積もりが高くなる傾向: 受注者側はリスク(仕様変更や予期せぬトラブル)を考慮して見積もりを出すため、費用が高くなることがある。
-
-
相性の良い開発手法: 事前に要件を固めるウォーターフォール開発と非常に相性が良いです。
2-2. 準委任契約(SES契約)
「業務(作業)の遂行」を目的とする契約です。受注者側は、システムを完成させる義務ではなく、契約期間中、善良な管理者としての注意をもって業務を遂行する義務(善管注意義務)を負います。エンジニアの技術力を「時間」を基準に提供する契約、と考えると分かりやすいでしょう。 IT業界でよく聞かれるSES(System Engineering Service)契約は、この準委任契約の一種です。
-
メリット(発注者側):
-
仕様変更に柔軟に対応できる: 開発途中で仕様の変更や追加が発生しても、契約の範囲内で柔軟に対応を依頼できる。
-
必要な技術力を確保しやすい: 自社に不足しているスキルを持つエンジニアを、必要な期間だけ確保できる。
-
開発プロセスに関与しやすい: 自社のチームの一員のようにエンジニアが作業するため、開発の状況を把握しやすい。
-
-
デメリット(発注者側):
-
成果物の完成は保証されない: あくまで業務の遂行が目的なので、期間内にシステムが完成しなくても、受注者側の責任は問えない。
-
発注者側にも管理能力が必要: エンジニアに適切な指示を出し、プロジェクトを管理する能力が求められる。
-
指揮命令権がない: 発注者は、SES契約で来たエンジニアに対して、直接的な業務の指揮命令(例:「明日はこの作業をしろ」「残業しろ」など)を行うことはできません。これは偽装請負という違法行為にあたる可能性があります。
-
-
相性の良い開発手法: 仕様変更に柔軟に対応する必要があるアジャイル開発と非常に相性が良いです。
2-3. 派遣契約
準委任契約(SES)と混同されやすいですが、明確な違いがあります。派遣契約は、派遣会社と雇用関係にあるエンジニアを自社に派遣してもらい、自社の指揮命令下で業務を行わせる契約です。
-
準委任契約(SES)との最大の違い: 指揮命令権の所在です。準委任契約では指揮命令権は受注者側(エンジニアの所属会社)にありますが、派遣契約では発注者側(派遣先企業)にあります。これにより、発注者は派遣されてきたエンジニアに直接、業務の指示を出すことができます。
-
メリット(発注者側):
-
自社の管理下で開発を進められる: 自社の社員と同様に、直接指示を出しながら柔軟に業務を進めることができる。
-
-
デメリット(発注者側):
-
高度な管理能力が必須: エンジニアのスキル管理、タスク管理、勤怠管理など、全ての管理責任を発注者が負う必要がある。
-
偽装請負のリスク: 請負契約や準委任契約であるにもかかわらず、実態として発注者が指揮命令を行っていると「偽装請負」と見なされ、法律違反となるため注意が必要です。
-
システムを実現する方法の種類
「どんなシステムを作るか」が決まった後、「どうやって作るか」という実現方法にもいくつかの種類があります。予算や納期、求める機能の独自性などによって、最適なアプローチは異なります。
3-1. フルスクラッチ開発
既存のものを一切使わず、ゼロから完全にオーダーメイドでシステムを構築するアプローチです。「スクラッチ(scratch)」が「最初から」を意味することに由来します。
-
メリット:
-
自由度が最も高い: デザイン、機能、業務フローなど、あらゆる要素を自社の要件に合わせて自由に設計・開発できる。
-
独自の強みを発揮できる: 競合他社にはない、独自の機能やサービスを実現し、競争優位性を築くことができる。
-
拡張性が高い: 将来的な事業拡大や仕様変更にも柔軟に対応しやすい設計が可能。
-
-
デメリット:
-
開発コストが最も高額になる: 全てをゼロから作るため、多大な人件費と時間が必要。
-
開発期間が長期化する: 要件定義からリリースまで、年単位の期間がかかることも珍しくない。
-
開発会社の選定が非常に重要: プロジェクトの成否が、開発会社の技術力や経験に大きく依存する。
-
3-2. パッケージ開発
特定の業務(会計、人事、販売管理など)向けに、既製品として販売されているソフトウェア(パッケージソフトウェア)をベースに、自社の業務に合わせて必要な部分だけをカスタマイズして導入するアプローチです。
-
メリット:
-
コストを抑えられる: フルスクラッチに比べて、開発コストを大幅に削減できる。
-
短期間で導入できる: ゼロから作る必要がないため、導入までの期間が短い。
-
業界の標準的な業務ノウハウが組み込まれている: ベストプラクティスが反映されていることが多く、業務プロセスの見直しにも繋がる。
-
-
デメリット:
-
カスタマイズに限界がある: パッケージの基本設計から逸脱するような、大幅なカスタマイズは難しい、あるいは非常に高コストになる。
-
独自性を出しにくい: 他社も同じパッケージを使っている場合が多く、差別化が図りにくい。
-
業務をパッケージに合わせる必要がある: パッケージの仕様に、自社の業務フローを合わせなければならない場合がある。
-
3-3. SaaS/ASPの利用
SaaS(Software as a Service)やASP(Application Service Provider)は、インターネット経由で提供されるソフトウェアサービスです。自社でシステムを構築・保有するのではなく、月額料金などを支払ってサービスを「利用」する形になります。
-
メリット:
-
導入が極めて迅速かつ安価: アカウントを契約すればすぐに利用開始でき、初期費用も安価なことが多い。
-
運用・保守が不要: サーバーの管理、セキュリティ対策、バージョンアップなどは全てサービス提供事業者が行ってくれる。
-
場所を選ばずに利用できる: インターネット環境があれば、PCやスマートフォンからいつでもどこでも利用できる。
-
-
デメリット:
-
カスタマイズがほぼ不可能: 提供されている機能やデザインをそのまま使うのが基本で、自社独自の要件に合わせることはできない。
-
他システムとの連携に制約がある: 外部連携用のAPIが提供されていない場合、他システムとのデータ連携が難しい。
-
サービスに依存する: サービス提供事業者がサービスを終了してしまったり、大幅な料金改定を行ったりするリスクがある。
-
3-4. ローコード/ノーコード開発
ソースコードの記述を最小限に抑える(ローコード)、あるいは全く記述しない(ノーコード)で、アプリケーションを開発できるプラットフォームを利用するアプローチです。画面上で部品をドラッグ&ドロップするなど、視覚的な操作で開発を進められます。
-
メリット:
-
開発スピードが圧倒的に速い: プログラミングの手間が大幅に削減されるため、短期間でアプリケーションを開発できる。
-
非エンジニアでも開発可能: 専門的なプログラミング知識がない業務部門の担当者でも、簡単なアプリケーションなら自ら開発できる(市民開発)。
-
コストを削減できる: 開発工数が減るため、人件費を抑えられる。
-
-
デメリット:
-
複雑な処理や大規模開発には不向き: プラットフォームが提供する機能の範囲内でしか開発できず、複雑なロジックや大規模なデータ処理には対応できない場合がある。
-
プラットフォームに依存する: 料金体系や機能、サービスの継続性などが、利用するプラットフォームに完全に依存する。
-
セキュリティやパフォーマンスの懸念: プラットフォームの仕様によっては、細かいセキュリティ設定やパフォーマンスチューニングが難しい場合がある。
-
開発されるシステムそのものの種類
ここまでは開発の「方法」に着目してきましたが、開発対象となる「システム」そのものにも様々な種類があります。対象によって、求められる技術や開発手法も異なります。
-
4-1. Webシステム(Webアプリケーション): Webブラウザを通じて利用するシステム全般。ECサイト、SNS、SaaS、予約システムなど、最も身近なシステムの一つ。
-
4-2. 業務システム: 企業の業務を支援するためのシステム。大きく2つに分けられる。
-
基幹系システム: 販売、会計、人事、生産など、企業の事業活動の根幹を担うシステム。止まると事業が継続できなくなるため、高い信頼性と安定性が求められる(例:ERP, SCM)。
-
情報系システム: 情報共有やコミュニケーション、意思決定を支援するシステム。直接的に事業の根幹を支えるわけではないが、業務の効率化に貢献する(例:グループウェア、社内SNS)。
-
-
4-3. モバイルアプリケーション: スマートフォンやタブレットで動作するアプリケーション。OSごとに開発する「ネイティブアプリ」、Web技術で作る「Webアプリ」、両方の特性を持つ「ハイブリッドアプリ」などの種類がある。
-
4-4. 組み込みシステム・制御システム: 家電製品、自動車、産業機械などの機器に組み込まれ、特定の機能を実現するためのコンピュータシステム。極めて高いリアルタイム性、安全性、信頼性が求められる。
-
4-5. AI(人工知能)システム: 画像認識、自然言語処理、需要予測など、AI技術を活用したシステム。データの収集・学習と、推論モデルの構築・評価という、従来のシステム開発とは異なるプロセスが必要となる。
-
4-6. IoTシステム: モノ(センサーやデバイス)をインターネットに接続し、相互に情報交換させることで、遠隔監視や自動制御などを実現するシステム。デバイス、ネットワーク、クラウド、アプリケーションといった多様な技術要素が絡み合う。
最適なシステム開発の種類を選ぶためのポイント
これまで見てきたように、システム開発には多種多様な「種類」が存在します。では、自社のプロジェクトにとって最適な選択をするには、何を基準に考えれば良いのでしょうか。最後に、そのための5つの重要なポイントを解説します。
5-1. 目的とゴールを明確にする
「何のためにそのシステムを作るのか?」という目的を、可能な限り具体的に定義することが全ての出発点です。「業務を効率化したい」という曖昧な目的ではなく、「手作業で行っている月次の請求書発行プロセスを自動化し、作業時間を月間80時間から8時間に短縮する」といったレベルまで具体化します。この目的が、開発手法やアプローチを選ぶ上での最も重要な羅針盤となります。
5-2. 要件の確定度を見極める
開発を始める前に、システムの仕様や機能をどこまで詳細に決められるかを見極めます。
-
要件がほぼ確定している場合: 法律の要件や、既存システムのリプレイスなど、作るべきものが明確な場合は、計画的に進められるウォーターフォール開発と請負契約の組み合わせが適しています。
-
要件が不確定・変化する場合: 新規サービスやユーザーの反応を見ながら改善したい場合は、柔軟に対応できるアジャイル開発と準委任契約の組み合わせが最適です。まずはプロトタイプで方向性を探るのも良いでしょう。
5-3. 予算と納期を考慮する
予算と納期は、開発アプローチを選択する上で大きな制約条件となります。
-
潤沢な予算と時間がある場合: 競争優位性を築きたいのであれば、フルスクラッチ開発で理想のシステムを追求できます。
-
予算と納期が限られている場合: パッケージ開発やSaaSの利用、ローコード/ノーコード開発が現実的な選択肢となります。最低限の機能(MVP: Minimum Viable Product)から始めて、段階的に拡張していくアジャイル的なアプローチも有効です。
5-4. 開発後の運用・保守を見据える
システムは作って終わりではありません。リリース後の運用・保守、将来的な機能拡張や改修も視野に入れておく必要があります。
-
自社に運用体制がない場合: 運用・保守をサービス提供事業者に任せられるSaaSは非常に魅力的です。
-
将来的な拡張性を重視する場合: フルスクラッチ開発であれば、長期的な視点に立った柔軟な設計が可能です。パッケージ開発の場合は、将来必要となりそうな機能もカバーできるか、拡張性があるかを確認する必要があります。
5-5. 外部パートナーとの関係性を考える
開発を外部に委託する場合、どのような関係性でプロジェクトを進めたいかを考えます。
-
仕様を固めてお任せしたい場合: 請負契約が適しています。ただし、信頼できるベンダーを慎重に選定する必要があります。
-
パートナーと協働し、一緒に作り上げたい場合: 準委任契約を結び、自社のチームの一員として参画してもらうことで、密なコミュニケーションを取りながら開発を進められます。この場合、発注者側にもプロジェクトをリードする能力が求められます。
まとめ
この記事では、システム開発における「開発手法」「契約形態」「開発アプローチ」といった様々な「種類」について、その特徴と選び方を解説してきました。
重要なのは、これらの種類の中に「どれか一つだけが絶対的に優れている」というものは存在しない、ということです。システム開発を成功に導く鍵は、プロジェクトの目的、特性、制約条件を正しく理解し、それぞれに最適な「種類」を賢く組み合わせることにあります。
例えば、「要件が不確定な新規Webサービス(対象システム)を、限られた予算と納期(制約条件)で立ち上げたい」というケースを考えてみましょう。この場合、
-
開発手法: 変化に強いアジャイル開発(スクラム)
-
契約形態: 柔軟に進められる準委任契約
-
開発アプローチ: まずはSaaSやローコードで素早く市場に投入し、ユーザーの反応を見てから、必要な部分をフルスクラッチで開発する
といった組み合わせが、非常に有効な戦略となり得ます。
システム開発は、決して簡単な道のりではありません。しかし、最初に正しい「種類」を選択することで、その成功確率は劇的に高まります。本記事が、これからシステム開発という航海に出る皆さまにとって、信頼できる海図となることを心から願っています。